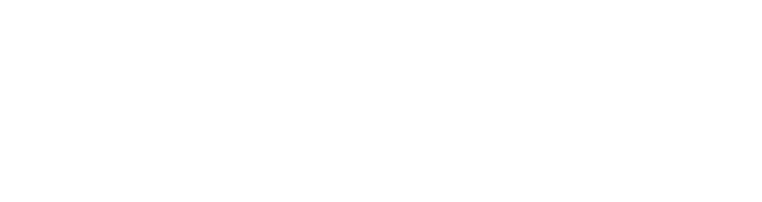- HOME>
- ドクターズインタビュー

interview 01
再生医療との出会いは?
私が再生医療と出会ったのは2002年、アメリカのピッツバーグ大学に留学していた時です。当初は椎間板の専門家として、椎間板の遺伝子治療に取り組んでいました。しかし、その留学の間に幹細胞治療という新しい分野と出会い、再生医療の可能性を知ったのです。

interview 02
再生医療の魅力や目指すところは?
人間の体は年齢を重ねるにつれて椎間板や軟骨が変性していき、一度傷んだら元には戻りません。こうした現実に対して、再生医療は大きく言えば「痛んだ組織を元に戻す」ことを目指しています。しかしこれは至難の技で、現実的には「痛んでいく組織の変性を遅らせる」ことが重要となります。変性のスピードを遅くするための手段として、遺伝子治療や幹細胞治療が有効と考えられています。
人間の変性、すなわち「老化」という現象は避けられないものです。しかし、それを遅らせて長持ちさせることは可能です。再生医療はそうした老化現象の進行を緩やかにするための重要な手段となります。

interview 03
帰国後の活動については?
留学から帰国した後、大学の非常勤講師として再生医療の「臨床応用」に力を注ぎました。再生医療が将来の治療になっていくとの確信を胸に、「人に使える段階まで持っていく」ということを目指して大学で基礎研究を続けました。
2011年にクリニック開業
再生医療の臨床応用を目指して

interview 04
クリニックを開業した思いは?
「再生医療の臨床応用を進めていきたい」という思いから、クリニックを開業しました。開業は平成23年(2011年)なのですが、その後、平成26年(2014年)に「再生医療等安全性確保法」が施行され、私たちの活動に大きな影響を与えることとなりました。この新法が施行されたことで、クリニックで再生医療を適用していけるようになったというわけです。

interview 05
研究会も立ち上げられている?
「脂肪幹細胞研究会」の立ち上げも、当院の再生医療に関わる大きなトピックの1つです。代表世話人もつとめております。
コロナ禍を除き、平成27年(2015年)に初めて開かれて以来、毎年開催されていて、2023年ですでに8回目となります。
研究会には日本全国から有志の医師および研究者や企業が集まってきます。参加者の多くが、大学病院、市中病院、クリニック等の医師、また企業からの参加も多く、毎年100名以上の方に参加いただいております。
こうした方々と共に活動できていることはとても光栄に思っています。
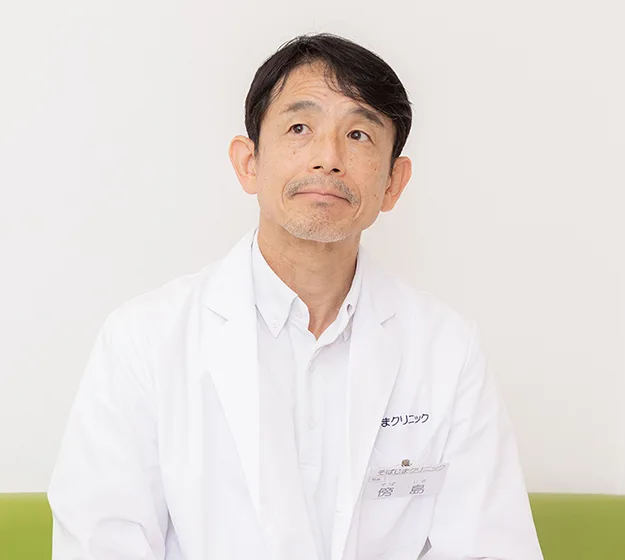
interview 06
活動が評価されている理由は?
20年来、幹細胞を研究しその臨床応用を目指し、自身も努力しました。
また、同じく臨床応用を目指す他の研究者や医師たちと共にこの治療のエビデンスをつみあげてきたからでしょうか。
すでに多くの応用研究を行っていたため、同じく臨床応用を目指す他の研究者たちと共に研究会を盛り上げていくことができました。
専門家との共同研究
情報発信に力を入れる

interview 07
共同研究では
どのような取り組みを?
再生医療は、私たちが行っている変形性関節症への治療だけに留まらず、様々な分野に応用可能です。進行度の異なる研究が各地で行われており、それらの研究者との連携を通じて、得られた細胞を有効に活用した基礎研究の成果を積み重ねています。
全国の研究者、特に大学の先生方から「一緒に研究を行いたい」「臨床応用を目指したい」とご連絡いただいており、そうした専門家と協力しながら共同研究を行っています。

interview 08
神戸大学医学部整形外科・
黒田良祐教授との関係は?
黒田先生との関係も、当院の再生医療を語る上で決して欠かすことのできない重要なトピックです。黒田先生と私はピッツバーグでの留学仲間です。黒田先生は教授となり、私はクリニックを開業するといった違う道を選んだものの、臨床研究への志は同じでした。
黒田先生と共に、当院の再生医療のプロジェクトを立ち上げ、神戸大学が共同研究という形で参加することになりました。これにより当院では現在、神戸大学の先生方に診療をお手伝いいただいているだけでなく、共同で研究も行っています。また一緒に論文を執筆し、治療のエビデンスを日本だけでなく世界中に発信しています。
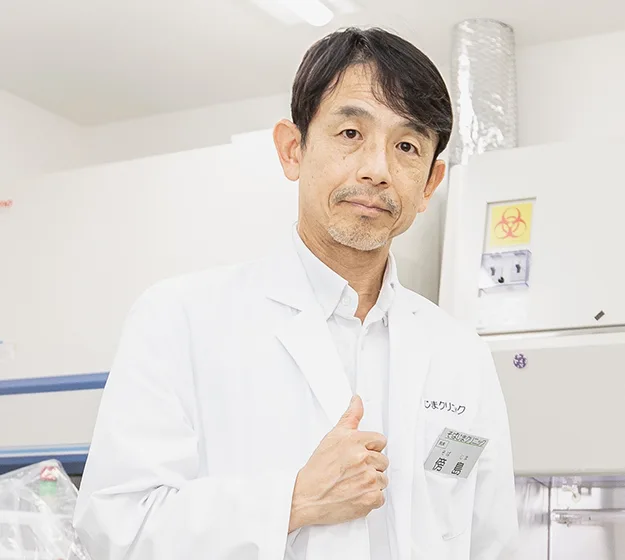
interview 09
情報の発信にも力を入れている?
私たちが行う治療は、科学的な「エビデンス」に基づいています。新しい治療方法を提案するためには、その根拠となる証拠を作り上げることが最も重要です。証拠がなければ、他の医師は新しい方法を試そうとは思わないでしょう。なので、今、将来に向けて証拠を作り上げているところです。

interview 10
新しい方法を試すのは大変では?
そうかもしれませんが、新しい治療方法を試し、その結果を論文として残すことは、医学の進歩には欠かせない要素です。大学の教授方はそうした研究活動を主に行っていますが、実際には大学内での再生医療の臨床研究には様々な制約があり、なかなか進めにくいという現実もあるようです。
動きづらい状況にある大学の先生方と協力して、一緒にエビデンスの構築を行っています。お互いに支え合いながら、前進しているというわけです。私としても、こうした活動に使命感を持って取り組み、留学から帰国して20年近く経った今、少しずつ形になってきていると感じています。
再生医療は標準治療の上に成り立つもの
既存の治療との組み合わせが重要

interview 11
再生医療で
大切に考えていることは?
再生医療は新しい治療方法として注目されていて、「特別な治療」のように思われがちですが、診察や学会活動で強調しているのは「既存の治療方法も重要である」ということです。「再生医療だけを頼りにしてはいけない」「既存の治療方法も組み合わせることが大事」ということをお伝えしています。この理解が進むことで、再生医療の位置づけやその有効性についての理解が深まると考えています。

interview 12
それは現状の再生医療の限界を
理解しているからこそ?
その通りです。現状の限界を超えていくためにはさらなる研究が必要で、再生医療がこれから進むべき重要な道筋だと考えています。

interview 13
普段の診療で大切にしていることは?
一番大切にしているのは、「患者様への診察をしっかりと行う」ことです。これが基本であり、最も重要なポイントです。患者様がこれまでに受けてきた治療の内容をしっかりと把握し、再生医療を検討する前に、患者様が標準治療をきちんと受けているかということを確認しています。なぜなら、再生医療はその標準治療の上に加えていくものだからです。
再生医療の発展の「架け橋」となるために
今後もエビデンスを構築していく

interview 14
最後に、ホームページを
ご覧になる方へ伝えたいことは?
新しい治療方法の導入にあたっては、既存の治療と、どのように融合していくかが重要です。既存の治療をしっかりと見極めた上で、新しい治療を組み込む姿勢が大切です。再生医療の特性を理解し、それを効果的に活用していきたいと思っています。これはどのような疾患に対しても言えることで、その疾患に対する適切な治療方法を行い、それを基に新たな治療を適用することで、治療の効果を最大化できるのです。
これが当院の再生医療の基本姿勢で、治療が間違った方向へ行かないように、専門家と治療方針を討議しながら進めていきます。そして再生医療のさらなる発展のために、今後も各分野の専門家とアライアンスを結び、共に議論をしながらエビデンスをしっかりと積み上げていきます。これが私の願いであり、将来、再生医療が発展していくための「架け橋」になると信じています。